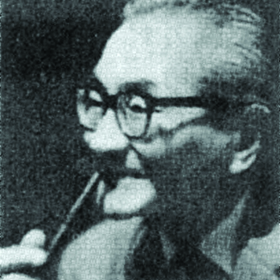柳澤木工所との出会い
伊東安兵衛氏
昭和40年2月執筆
もう十五ねんも前になるだろうか。
松本市と長野県民芸協会とが主体となって、松本市の民芸の振興を図ることとなり、年に一回、各地から講師を招いて指導にあたらせたことがあった。
私は松本の木工家具の振興についてお手伝いすることになり、松本市に招かれた。私は木工家具には強い関心をもっていたが、専門家というわけではなく、とにかくまつもとへ行って多くの製作者と会い、一応の意見を述べたり、デザインをしたりした。
私の滞在は三日間ほどだったが、その翌日の朝、宿に寝込みをおそった者があった。それは柳沢さんという人で、用件を聞いてみると、その人は現在ラジオのキャビネットを主に作っている小さな工場を経営しているが、「今の仕事にあきたりないので、なんとかして、もう少しやりがいのある仕事をしたい。ついてはぜひとも私に力になってほしい。今後は民芸木工を作ってゆきたい」という希望を一生懸命のべた。
その熱心な態度に私も動かされ、はたしてどれほどのことが出来るかわからないが、私がやれることだったら何なりとお手伝いしようということになり、これが機縁で、それからはこの工場で作るものの大部分に私のいきがかかることになった。
この工場は設備も大したことはなく、また工員が大ぜいいるわけでもなく、民芸木工を作るといっても大きな家具類などはとても無理だと思ったので、小木工を作ることにした。はじめは暗中模索で、たあいのないものを作っていたが、次々と作っていくうちには、ずいぶんといろいろなものが出来るようになった。
すでに十数年になるわけで、一日一日と重ねてゆく努力によって、現在では松本の小木工を代表するといってもよいようなものも作られ、間に合わぬくらいよく売れているとのことだ。その間、柳宗悦先生はじめ日本民芸協会の方々の応援もあり、少しずつながら見るべきものもふえてきたのは誠に幸いであった。
ところが、たいへん残念なことには、この仕事をはじめてから何年ぐらいたったころか、そろそろ軌道にのりはじめたころ柳沢さんは亡くなられてしまった。主人を失って、さてどうしょうかと迷った柳沢さんの未亡人は、けなげにもその後をひきうけ、このしごとを続けることになった。一生懸命ということはえらいもので、それから現在にいたるまでには、徐々に設備も改まり、生産もふえていった。
現在、松本で作られている小木工は、たいへん種類がおおく、小箱やたなの類から、電気セード、電気スタンド、あんどん、マガジンラック、状差し、帽子掛け、掛け鏡、額縁、運び盆、徳利はかま、燭台、さら立てなどさまざまのものがある。材はほとんどが ケヤキで、これを「ふきうるし」に似せた色で塗装しているが、ケヤキであるだけに、木目が美しく、一般に市販されている木工類よりははるかに堅牢で、重みが感じられる。また誠実な仕事がされていることも特徴となっている。”ごまかし”のないところが、民芸木工の値うちだといえるだろう。それに、よい技術者をのがさずに長くかかえていることも感心される。多少高くなっても、品質を落とさぬ方針を守っていることも立派なことと思う。しかし何としても小規模で、零細企業の名がそのままあてはまるような生産で、需要がふえても、なまじ大きくしないところが、かえって品質を保持していく道なのかもしれない。長野県下にこのような木工品が作られていることは、ささやかではあっても県の産業の小さなにない手としてみとめられていいのではないだろうか。
 あんどん型の電気スタンド
あんどん型の電気スタンド
伊東安兵衛氏デザイン